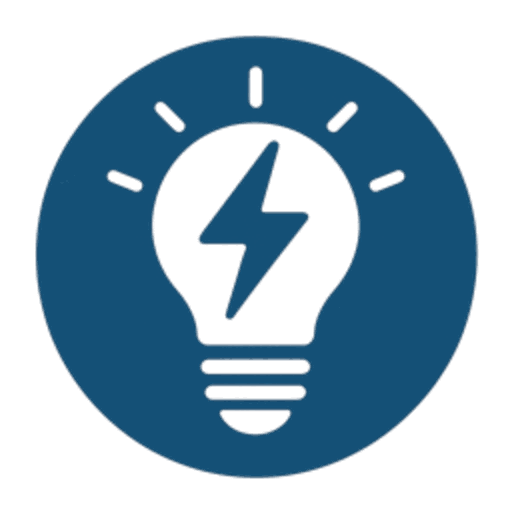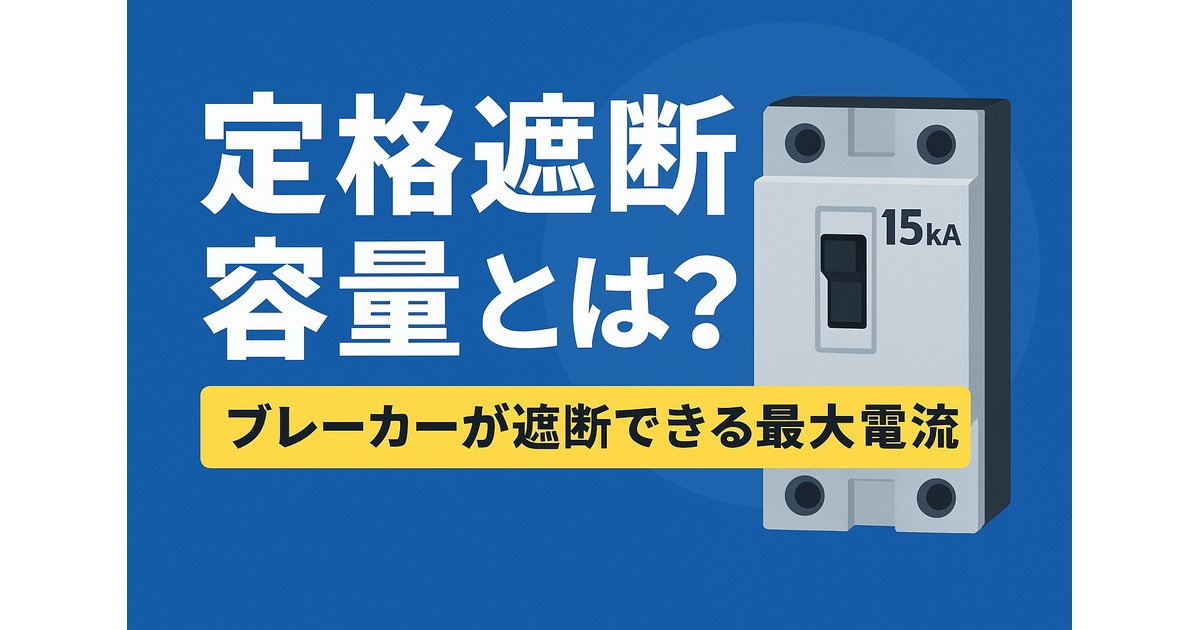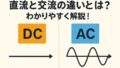今回は「定格遮断容量(Interrupting Capacity)」について解説します。
ブレーカーの選定では「定格遮断容量(Interrupting Capacity」を理解しておくことが非常に重要です。
特に短絡電流(ショート時に流れる電流)に対応できるかどうかがポイントです。
定格遮断容量とは?
◆ざっくり言うと
「ブレーカーが正常に遮断できる電流の最大値」のことです。
◆もう少し具体的な例で言うと、
万が一、ショート(短絡)が起きて、大きな電流が流れたときに、
そのブレーカーが壊れずに止められる限界の電流値のことです。
◆たとえば、
”定格遮断容量が15kAのブレーカーなら、
それ以下の短絡電流であれば安全に遮断してくれる”ということです。
なぜ定格遮断容量が需要なのか?
正直、定格遮断容量を考えなくても、
電源はONし設備は稼動します。
ですが、、
”もし”短絡した発生した場合、
感電や火災のリスクがあります。
自分が設計した設備で事故が起きてしまったら…。
想像するだけでゾっとしますよね。
だからこそ、
現場で予想される最大短絡電流よりも遮断容量が上回るブレーカーを選ぶことが重要なのです。
アウトな選定方法
以下のような選定は完全にNGです。
・予想される最大短絡電流:12kA
・使用するブレーカーの定格遮断容量:10kA
この場合、ブレーカーが想定を超えた電流に耐えられず、うまく遮断されません。
⇒より大きな遮断容量を持つブレーカー(例:15kAなど)に変更しましょう。
定格遮断容量はどこに書いてあるの?
ブレーカーの本体や、仕様書などにしっかり記載されています。
「10kA」や「15kA」と、kA(キロアンペア)単位で書かれることが多いです。
まとめ
・定格遮断容量とは、ブレーカーが安全に遮断できる最大電流のこと。
・遮断容量が不足すると、感電・火災などのリスクあり。
・予想される最大短絡電流よりも、遮断容量が上回るブレーカーを選定しよう。
・定格遮断容量は、本体や仕様書に書かれている。
設備の安全は、細かな設計が大切です。
定格電流ではなく、遮断容量にも注目してみてください。
よくある質問
Q.家庭用ブレーカーにも定格遮断容量ってあるの?
⇒はい、あります。
家庭用でも短絡が起きる可能性があるため、適切な遮断容量の製品が使われています。
Q.遮断容量は高ければ高いほどいいの?
⇒安全性は高まりますが、コストやサイズを考えて選定しましょう。