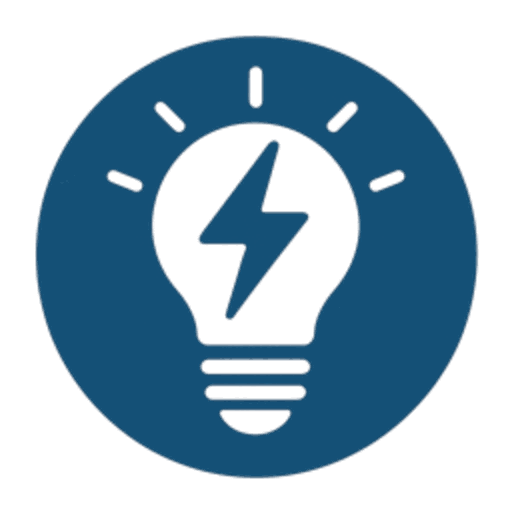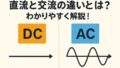はじめに
サーキットプロテクタは、産業機器や制御機器の保護回路に欠かせない安全装置です。
この記事では、その仕組みや特徴に加えて、用途に応じた選定方法までわかりやすく解説します。
これから導入を検討している方は、でひ参考にしてください。
サーキットプロテクタとは?
サーキットプロテクタは、低容量の電気回路を過電流から保護するための安全装置です。
電流が過剰に流れると、内部の機器や配線が発熱・損傷する恐れがあります。
サーキットプロテクタは、それを未然に防ぐために回路を遮断する役割を持ちます。
サーキットプロテクタの仕組み
多くのサーキットプロテクタには、
バイメタルと呼ばれる金属が使用されています。
このバイメタルは、温度によって曲がる性質があり、
流れる電流が多すぎると熱が発生し、
金属が曲がって回路を遮断する仕組みです。
・過電流発生→発熱→バイメタルが曲がる→回路遮断
主な特徴と役割
・過電流保護:電流が異常に大きくなると自動的に回路を遮断。
・再使用可能:ヒューズと違い、一度作動してもリセットして再利用できるものが多い。
代表例:三菱電機 CP-30BA
・小型:小型なものが多く、制御盤などで少ないスペースで設計可能
ヒューズやブレーカーとの違いは?
| 項目 | ヒューズ | ブレーカー | サーキットプロテクタ |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | 使い捨て(溶断) | 再利用可能(手動復帰) | 再利用可能(自動または手動復帰) |
| サイズ | 小型 | やや大きい | 小型 |
| 主な用途 | 家電・電子機器 | 住宅・商業施設・工場 | 制御機器・産業機器 |
| 交換の手間 | 必要(切れたら交換) | 不要(ON/OFFで復帰) | 不要(リセットまたは自動復帰) |
| コスト | 安価 | 中〜高 | 中 |
現場で失敗しないサーキットプロテクタの選び方
適切なサーキットプロテクタを選ぶには、下記のポイントを確認しましょう。
1:定格電流
定格電流を決める保護したい回路の最大電流に応じて選定します。
通常は負荷電流の1.25〜1.5倍程度が目安となってます。
例:負荷電流が2Aであれば、3Aの定格電流を持つサーキットプロテクタが候補になります。
2:動作特性(トリップ特性)
過電流が発生してから遮断するまでの時間も重要です。
負荷の性質により、即遮断がよい場合と、多少の突入電流を許容したい場合があります。
今回は三菱電機のCP30-BAを例に紹介します。
・瞬時形:電子回路向け、瞬時の過電流に敏感に反応
・中速形:モーターなどの突入電流に対応
・低速形:突入電流が大きい回路に最適
*用途に応じてトリップ特性を確認しましょう。
3:復帰方式
・手動復帰型:誤動作のリスクが低い。安全第一の現場に向いている。
・自動復帰型:無人設備など、復旧が自動で済む現場に向いている。
4:設置方法と形状
DINレールやパネル取り付けなどに適したサイズと形状を選びましょう。
また、使用環境(温度・湿度・振動)に応じた耐環境性も重要です。
よくある失敗例
・定格電流が低すぎて、頻繁にトリップしてしまう。
・サイズが合わず、盤に収まらなかった。
・突入電流でトリップしてしまう。
どれも仕様の見落としが原因です。カタログや仕様をよく確認し、選定を行いましょう!
まとめ
サーキットプロテクタは、電子回路や制御機器の過電流保護に不可欠な装置です。
ヒューズやブレーカーと異なる独自の特徴を持ち、適切な選定により、安全性と効率性が大きく向上します。
導入前には、定格電流・トリップ特性・復帰方式・設置条件などをしっかり確認しましょう。
関連記事
三菱 CP30-BAを基礎から解説!初心者・新入社員が知っておくべき仕様まとめ